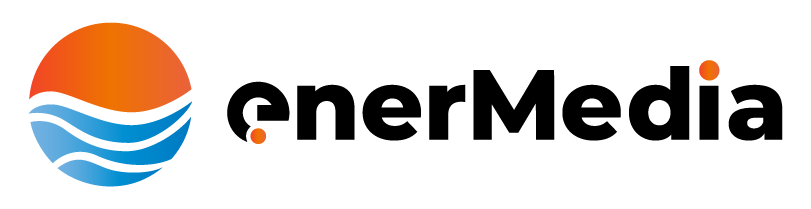2025 新規事業の用語集

-戦略立案から組織開発まで、使い分けで差がつく-
EnerMediaをご覧の方の中でも「フレームワークは知っているけど、どれをいつ使えばいいのか分からない」そんな悩みを抱える方は少なくないのではないでしょうか?
エナジャイズでは本記事で紹介するフレームワーク以外にも様々な手法を用いて業務を進めておりますが、世の中にはフレームワークがたくさんあります。
今回の記事ではご参考になるかもしれないフレームワーク例を数種類、紹介させていただきます。

1. 戦略設計 – 未来を描くための視座を持つために【PEST分析・ SWOT分析】
新規事業の戦略立案の設計に欠かせないのは、まず外部環境を正しく読み解くこと。
そこで活用されるのが【PEST分析】です。
政治(Politics)・経済(Economy)・社会(Society)・技術(Technology)の4要素を軸に、事業に影響を与える外部環境を整理します。
- 政治(Politics)
政治制度や法制度、税制などの観点から、自社に影響を及ぼす外部要因を分析します。
具体的な分析対象には、法規制や規制緩和、政府の政策方針、税制改正はもちろんのこと、政府機関や市民団体(例:NPO)の動向、司法判断の変化(例:最高裁判決の変更)、外交関係の推移などが含まれます。
- 経済(Economy)
マクロ経済の変動が自社の事業環境に与える影響を分析します。
主な分析項目には、景気動向、インフレ・デフレの進行、為替レート、金利水準、経済成長率、日銀短観、失業率、鉱工業生産指数などが挙げられます。
- 社会(Society)
消費者の価値観やライフスタイルの変化、社会全体の意識や構造的変化を指します。
具体的な項目としては、人口動態、世帯構成の変化、教育水準、社会意識、犯罪傾向、健康志向、環境問題、文化的潮流などが挙げられます。
- 技術(Technology)
技術の進展や革新がもたらすビジネスへの影響を分析するための視点です。
主な分析項目には、最新の技術開発動向、特許の取得状況、研究開発への投資傾向、情報通信技術の進化、オープンイノベーションの進展などが含まれます。
新市場への参入や、長期的なビジョン策定の初期段階におすすめです。一方で短期の分析には向いておらず、あくまで外部要因のみに注目するため、内部要因もしっかりと観察する必要性があります。
次に、企業の現状を俯瞰するために定番なのが SWOT分析。自社の強み・弱み(内部)と、機会・脅威(外部)を4象限に整理することで、自社が取るべき戦略の方向性が見えてきます。さらに一歩踏み込むなら、要素を掛け合わせて戦略を導く「クロスSWOT分析」まで活用しましょう。
「クロスSWOT分析」では縦軸に「強み」「弱み」、横軸に「機会」「脅威」を置き、それぞれの象限ごとに適切な戦略を配置します。こうすることで自社の強みや弱みに応じた際的な戦略設計を行うことができます。
2. マーケティング -顧客に届く戦略を立てるために【STP分析・4P/7P】
プロダクトを売れる状態に持っていくには、顧客の視点に立つことが何より重要です。
まずは STP分析(セグメンテーション/ターゲティング/ポジショニング)を使い、誰に、どのような価値を、どのような立ち位置で提供するかを整理しましょう。
そのうえで、具体的な施策設計に役立つのが 4P/7P フレームワークです。「4P」は聞いたことがある方も多いかもしれませんが、最近では7PまでPが増えたフレームワークも主流になりつつあります。
従来の4P分析で用いられていた「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「プロモーション(Promotion)」に加え、7Pでは「人(People)」「プロセス(Process)」「物的証拠(Physical Evidence)」までを対象とします。サービス業やD2Cビジネスなど、“人”の介在が大きいビジネスにとっては特に有効です。
「物的証拠(Physical Evidence)」は聞き馴染みが無い、という方も多いかもしれませんが、顧客の不安を払拭するための物的証拠(店舗の外装や内装、契約書なども含まれます)のことを指します。
顧客体験の全体像をつかむには「カスタマージャーニーマップ」の活用も有効です。
【認知→興味→検討→購入→継続】といった流れを時系列で見える化することで、顧客がどこで離脱しているのか、どのタッチポイントに改善の余地があるのかが明確になります。
3. 企画全般 -アイデアを事業に変えるために【ビジネスモデルキャンバス・JTBD(ジョブ理論)・Opportunity-Solution Tree】
新規事業やサービス企画において、アイデアを事業として形にする際に有効なのが「ビジネスモデルキャンバス」です。「ビジネスモデルキャンバス」では「顧客セグメント」「提供価値」「チャネル」「顧客との関係」「収益構造」「主要リソース」「主要なビジネス活動」「主要パートナー」「コスト構造」といった9つの要素を1枚にまとめることで、構想の全体像がクリアになります。
顧客ニーズを深く理解するなら、近年注目されている JTBD(ジョブ理論) がおすすめです。「顧客は何を“したくて”この商品・サービスを使うのか?」という視点から課題を再定義することで、より本質的な価値提供につながります。
複数のアイデアを評価・優先順位付けしたい場合には「Opportunity-Solution Tree(機会・解決策ツリー)」が効果的です。ユーザーの課題を起点に、機会→解決策→実験という順でブレイクダウンしていくことで、論理的に企画を整理できます。
4. 体制の構築 -実行可能な組織をつくるために【RACIチャート】
どんなに良い企画も、動かすチームが機能しなければ実現しません。役割分担を明確にするために有効なのが「RACIチャート」です。
「責任者(Responsible)」「最終決裁者(Accountable)」「相談相手(Consulted)」「情報共有先(Informed)」を定義することで、プロジェクトの停滞を防げます。
5. 組織開発 -チームの成長と文化を創るために【タックマンモデル・OKR】
組織づくりは、人とチームの成長と切り離せません。チームビルディングの観点から有効なのが「タックマンモデル(形成➡︎混乱➡︎統一➡︎成果の4段階)」です。チームが今どのフェーズにあるのかを理解することで、適切な対策の考案が可能になります。
1965年に心理学者のブルース・W・タックマン氏が提唱したこのモデルは60年前に発表されたものではありますが、現在でも応用可能で、人と人とが関わり合って事業を進めていくという点では60年前も現在も大きくは変わらないものです。
また、目標設定に迷う場合には「OKR」が有効です。単なる成果指標ではなく、挑戦的な目標と定量的な結果を結びつけることで、個人と組織の方向性を揃えることができます。
6. 問題解決 -本質を見抜く力を鍛えるために
日々の業務では、目の前の課題にどう向き合うかも重要です。
原因を深掘りする場面では「ロジックツリー」が特に有効です。問題を分解して可視化することで、見落としていた要因が明らかになることもあります。
シンプルで効果的な手法としては「5Whys(なぜを5回繰り返す「なぜなぜ分析」)」もあります。なぜ?を繰り返すことで、表面的な問題の背後にある根本原因に迫ります。一般的に5回「なぜ?」と掘り下げていくことによって根本的な原因に至ることができると言われています。
複数の選択肢を比較して意思決定するには デシジョンマトリクス(評価マトリクス)を活用しましょう。評価軸ごとに点数をつけることで、定量的な判断が可能になります。
本記事では、カテゴリ別にそれぞれ適したフレームワークについてご紹介しました。
フレームワークは知っているだけではあまり意味がなく、実際に使ってこそ、その効果を発揮します。
まずは、ご自身の業務をフレームワークに落とし込むことから始めていただくと、「これまでフレームワークなんて意識したことも無かった」という方でも徐々に慣れていっていただけるのではと思います、
最後に、1つのフレームワークだけに頼るのではなく、複数を組み合わせて「構造的に考える力」を鍛えていきましょう。
実際のビジネスの現場では、問題が複雑に絡み合っていたり状況も刻一刻変化したりしますので、1つだけではなく複数のフレームワークを使いながら対処を進めていただければと思います。
新規事業開発のご相談はエナジャイズまでお気軽にどうぞ!
60分無料カウンセリングを承ります!
こんな方はぜひお気軽にご相談ください!
顧客ニーズの汲み取り方がわからない
顧客検証の方法がわからない、手が回らない
アポが取れない、営業に苦手意識がある
株式会社エナジャイズ代表取締役岡崎 史
プロフィール
上場企業を中心に170の新規事業の立ち上げを経験後、
エナジャイズを創業。
徹底的に顧客視点に立つ独自の事業開発手法で、年商1,000億円以上の大企業向けの支援、研修、講演等実績多数。